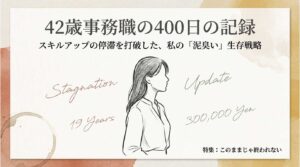たぶん、裏で「細かいよね」って言われてた
気づかないフリをしてたけど、たぶん言われてた。
私、勤続15年の古株事務員。
新人の女の子に、親切心で言ってたつもりだった。
「このファイルの保存名は、半角じゃなくて全角でね」
「メールのCCには、必ず課長を入れてね」
彼女たちは「はい、すいません」って言うけど、目が笑ってない。
給湯室でヒソヒソ話が聞こえると、心臓がキュッとなる。
ああ、私、「面倒くさいお局」になってるんだな。
飲み会に誘っても「あ、その日はちょっと…」って断られる。
バレンタインの義理チョコも、事務的な「ありがとうございます」だけ。
正直、ちょっと寂しかった。
でもまあ、40代ってこんなもんだよねって、自分に言い聞かせてた。
ある日の夕方
ある日の夕方。
新人の子が、残業して泣きそうな顔でExcelと睨めっこしてた。
「どうしたの?」って聞くと、
「顧客データ500件を、手作業で別シートに移してるんです…終わらなくて…」
昔の私なら、こう言ってたと思う。
「大変だね。でも、これも修行だから頑張って」
あるいは、手伝って恩を売ってたかもしれない。
その日は、なぜかそう言わなかった。
私が最近覚えた「VBA(マクロ)」の練習になるかも、と思った。
「ちょっと貸して」
「ちょっと貸して」
正直、うまくいくか自信なかった。
家で練習したコードを、ちょっと書き換えて。
たしか5分くらい?
もっとかかったかも。
「このボタン、押してみて」
彼女がクリックした。
…動いた。
3時間かかるはずの作業が、たぶん数秒で終わった。
自分でもビックリした。
彼女、目、丸くしてた
彼女、しばらく固まってた。
それから、私を見て言った。
「え…これ、どうやったんですか?」
目、丸くしてた。
「たいしたことないよ、VBAってやつ」
そう言って席に戻ろうとすると、彼女が追いかけてきた。
「すごいです! これも自動化できますか!?」
で、何日かして
で、何日かして。
若手社員たちが、私のところに話しかけてくる回数が増えた。
「細かい小言」を聞きに来るんじゃない。
「仕事を早く終わらせる方法」を聞きに来る。
別の子が、「〇〇さん、これもできますか?」って聞いてきた。
私は、また5分くらいコード書いた。
「これで、たぶんできるはず」
彼女が試してみると、できた。
「ありがとうございます! 助かりました!」
その時の「ありがとう」は、
義理チョコの時の「ありがとうございます」とは、違った。
たぶんだけど
たぶんだけど、
説教でも気遣いでもなくて、
「今日早く帰れるかどうか」だけだったんだと思う。
私、勘違いしてた。
今も、たぶん裏では
今も、たぶん裏では「細かい」って思われてる。
でも、「便利な人」とも思われてるはず。
それで、まあいいかなって。
飲み会に誘われる回数も増えた(断るけど)。
若い子と仲良くなったわけじゃない。
でも、「あ、〇〇さん」って話しかけられるようにはなった。
それだけで、十分だと思ってる。
もし、煙たがられてるかもって思ってるなら
もし、煙たがられてるかもって思ってるなら。
若い子の話題に無理して合わせなくてもいい。
精神論とか、語らなくてもいい。
ただ、エクセルをちょっと便利にできるだけで、
たぶん、見る目は変わる。
正直、好かれてはいないと思う。
でも、「いないとちょっと困る」くらいにはなれた。
承認欲求を満たすのに、インスタの「いいね」はいらない。
「〇〇さんのおかげで助かりました」
たぶん、それだけで、もういいかなって思えた。
追伸:私が使った「魔法の杖」
私が若手にドヤ顔するために使った「VBA」。
実は、たしか2,000円くらいの動画講座で覚えた。
「プログラミングなんて無理」と思ってた私が、どうやってこっそり覚えたのか。
その種明かしは、こちらに書いてあります。
👉 40代で未経験からプログラマーになろうとして、たぶん失敗した話(でも、生きてます)